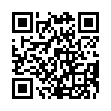Vinca Beta
興運院
基本情報
- 所在地
- 〒359-1151
埼玉県所沢市若狭4丁目2477-1 - TEL / FAX
- 04-2949-7494
- URL
- 業種
- 寺院
- コメント
- 最寄り駅
- 西武池袋線 狭山ヶ丘 290m
- 西武池袋線 武蔵藤沢 1500m
- 西武池袋線 小手指 2090m
- 周辺情報
- 所沢市立所沢図書館狭山ヶ丘分館 公共図書館
- JAいるま野狭山ヶ丘支店 銀行その他
- マミーマート狭山ヶ丘店 その他のスーパーマーケット
- サイゼリヤ狭山ヶ丘店 サイゼリヤ
- 狭山ヶ丘駅(西武) 駅(他社線)
- 東和銀行狭山ヶ丘支店 地方銀行
- ローソン所沢若狭店 ローソン
- 仁栄会所沢緑ケ丘病院 病院(動物は除く)
- 第二なかよしこども園 幼稚園
- 所沢若狭郵便局 中央、普通郵便局、特定郵便局、簡易郵便局
- 西武信用金庫狭山ヶ丘支店 信用金庫
- セブンイレブン狭山ヶ丘駅西口店 セブン-イレブン
- こでまり幼稚園 幼稚園
- ファミリーマートトモニー狭山ヶ丘駅店 ファミリーマート
ウィキペディア検索
- 真言宗智山派
- 興 教大師覚鑁(1095年 - 1144年)を開祖とする新義真言宗と呼ばれる宗派の中の一つ。天正5年(1577年)に根来山の能化職となった玄宥(1529年 - 1605年)が、天正13年(1585年)、秀吉による紀州征伐で焼き滅ぼされた根来山智積 院
- 松平親忠 (形原松平家)
- 天文10年(1541年)には東条城主・吉良義昭を攻めており、この時期には岡崎の松平広忠と同様、織田方への協力を余儀なくされた。 墓所は愛知県蒲郡市西浦町北馬場の光忠寺。法名は到 運院 殿峯誉西岸浄光。 ^ 『新訂寛政重修諸家譜』第1巻 ^ 蒲郡市形原町東古城 ^ 名古屋市守山区市場 ^ 愛知県西尾市吉良町駮馬 『新訂寛政重修諸家譜』
- 七日市藩
- ぶあきら)は「前田兵部家」、同じく利意の子・前田孝效(たかのり)は「前田式部家」を 興 した。 [脚注の使い方] ^ 明和4年(1767年)に小幡藩織田家が転出し、譜代の奥平家に交替。 ^ 利孝の生母は側室の明 運 尼(明 運院 。父は加賀一向一揆の指導者の一人で石浦に拠った山本家芸)で、慶安元年(1648年)に七日市で没している。
- 陶興房
- 興 房率いる大内軍には杉 興運 や仁保隆重、秋月氏、菊池氏、九州千葉氏、原田氏など北九州の主だった将が従った。しかし少弐資元の家臣・筑紫惟門が勝尾城で強く抵抗し、大友義鑑が筑前に侵攻して星野親忠を降伏させるなど苦戦が続いた。このため天文2年(1533年)2月には義隆より 興
- 細田博之
- 父・吉蔵の議員秘書を経て、1990年の衆議 院 選挙に島根県全県区から立候補し、竹下登、櫻内義雄に次ぐ3位で初当選(当選同期に福田康夫・岡田克也・佐田玄一郎・亀井久 興 ・中谷元・森英介・石原伸晃・河村建夫・小林興起・塩谷立・古屋圭司・松岡利勝・小坂憲次・山本拓・赤城徳彦・村田吉隆・簗瀬進・山本有二など)。1996年の第41回衆議 院
- 大内義隆
- 享禄3年(1530年)からは九州に出兵し、北九州の覇権を豊後国の大友氏や筑前国の少弐氏らと争う。家臣の杉 興運 や陶 興 房らに軍を預けて少弐氏を攻めた。そして肥前国の松浦氏を従属させ、さらに北九州沿岸を平定して大陸貿易の利権を掌握した。しかし杉 興運 に行なわせた少弐攻めでは、少弐氏の重臣・龍造寺家兼の反攻にあって大敗を喫した(田手畷の戦い)。
- 中野清茂
- 斉が死去し、水野忠邦が天保の改革を開始すると、登城を禁止されたうえ、加増地没収・別邸取り壊しの処分を受け、向島に逼塞し、その翌年に死去した。戒名は高 運院 殿石翁日勇大居士。 漢学者・五弓久文の『文恭公実録』によると、当時その豪奢な生活ぶりから、「天下の楽に先んじて楽しむ」三翁の一人に数えることわざが作
- 頂妙寺
- 常徳寺末:寂而山常照寺(奈良県高市郡高取町大字清水谷) 妙光山法蓮寺(神戸市兵庫区神明町) 日出山本妙寺(丹波市春日町東中) 一龍山妙長寺(福山市駅家町万能倉) 橋照山慈 運院 (倉吉市関金町安歩) 彼岸山積善寺(松山市鹿峰) 天高山妙國寺(高知市塩屋崎町) 妙國寺末:若一山本正寺(南国市田村甲) 妙國寺末:天高山細勝寺(南国市田村乙)
- 塩谷立
- 校関係者を動員するなど、選挙活動に当たる行為を行い公職選挙法に違反したのではないかとの疑いが浮上した。 自動車の運行・管理の受託を行っている日本道路 興運 から政治資金規正法により定められた上限750万円を超える、違法な献金を受け取っていたことが発覚した。報道によれば、塩谷は2000年~2003年まで
- 大寧寺の変
- もり、さらに隆房に詰問使を送るなどしたことから、義隆と隆房の仲は最悪の事態を迎えた。 天文20年(1551年)1月、出奔していた武任が筑前守護代の杉 興運 によって身柄を確保された。この一連の騒動で義隆から責任を追及されることを恐れた武任は、相良武任申状において弁明し、「陶隆房に謀反の疑いがあると主張し
企業データ
所沢ロイヤル病院 1.16km
カトリック青少年育成場 1.00km
株式会社葵 0.93km
株式会社山本建設 0.88km
ニシキ建設株式会社 0.84km
株式会社アキュラホーム/所沢若狭営業所 0.76km
能安寺 0.79km
大和ハウス工業株式会社/所沢展示場 0.71km
アドファスハウジング株式会社 0.71km
所沢西郵便局/貯金・保険 0.79km
所沢西郵便局/郵便集荷 0.79km
所沢西郵便局/郵便配達 0.79km
よしかわ通所リハビリテーション道 0.75km
真宗大谷派西栄寺 1.10km
浄土真宗東本願寺真宗大谷派西栄寺 1.10km
産経建設株式会社 0.65km
浄土真宗東本願寺真宗大谷派西栄寺 1.08km
西埼玉中央病院 0.86km
スーパーバッグ労働組合 0.51km
柴田工務店株式会社 0.40km
所沢市立児童館わかば 1.05km
中小企業総合支援管理組合 0.32km
株式会社原測量 0.59km
リビングライフ・サイシン 0.80km
西武信用金庫/狭山ケ丘支店 0.27km
所沢若狭郵便局 0.23km
所沢市立若狭学童クラブ 0.16km
JAいるま野/狭山ケ丘農産物直売所 0.05km
所沢市役所/老人福祉センター/さやまがおか荘 0.03km
所沢市役所/市民課サービスコーナー/狭山ケ丘サービスコーナー 0.03km
所沢市立所沢図書館/狭山ケ丘分館 0.03km
所沢市立児童館すみれ 0.21km
緑ヶ丘居宅介護支援事業所 0.16km
所沢緑ケ丘病院 0.16km
JAいるま野/狭山ケ丘支店 0.04km
介護老人福祉施設平安の森 0.93km
ミカシマ建設株式会社 0.09km
西ところざわ翔裕館 0.90km
明生リハビリテーション病院 0.91km
株式会社東和銀行/狭山ケ丘支店 0.15km
さけみ眼科 0.15km
荻野医院 0.18km
介護老人保健施設遊 1.10km
アポロ工業株式会社 0.68km
埼玉県警察署 0.25km
圏央所沢病院 1.03km
所沢市役所/狭山ケ丘区画整理事務所 0.75km
飯能信用金庫/狭山ケ丘支店 0.47km
ジョイリハ狭山ケ丘 0.44km
株式会社相互開発 0.50km
狭山ヶ丘チャペル 0.62km
株式会社青山工務店 0.56km
トリプルナインみんなの家 0.78km
綜合美装建設株式会社 0.62km
ニューライフ・ファミリーチャーチ 0.75km
浄土真宗法瑠寺 0.70km
株式会社メイクホームズ 0.68km
吉祥院 1.19km
リーディング・ジャパン株式会社 0.75km
ねっこぼっこの家 0.91km
入間市立藤沢東学童保育室 1.06km
介護老人保健施設ケアステーション所沢 1.15km
松風荘病院 0.92km
日南技術株式会社/入間営業所 1.17km
株式会社昭計/所沢営業所 0.98km
株式会社昭計/本社 0.98km
入間市役所/東藤沢地域包括支援センター 0.97km
特別養護老人ホーム康寿園 1.16km
光の園 1.18km
皆成会 1.18km
入間市役所/東藤沢出張所 1.01km
一期庵 1.03km
大東ガス株式会社 1.15km
小宮山医院 1.17km