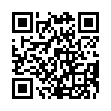Vinca Beta
敷島神社
基本情報
- 所在地
- 〒354-0011
埼玉県富士見市大字水子1762 - TEL / FAX
- 049-251-7520
- URL
- 業種
- 神社
- コメント
- 最寄り駅
- 東武東上本線 みずほ台 1470m
- 東武東上本線 柳瀬川 1780m
- 東武東上本線 鶴瀬 2170m
- 周辺情報
- 水子貝塚公園 観光公園
- 富士見市立水子貝塚資料館 各種資料館
- 富士見市立本郷中学校 中学
- 富士見市立水谷小学校 小学
ウィキペディア検索
- 敷島神社
- 敷島神社 (しきじまじんじゃ) 敷島神社 (志木市) - 埼玉県志木市に鎮座する 神社 。 敷島神社 (吉野川市) - 徳島県吉野川市に鎮座する 神社 。 敷島神社 (対馬市) - 長崎県対馬市に鎮座する 神社 。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のた
- 志木市
- 立善講寺 御嶽 神社 敷島神社 - 境内に重要有形民俗文化財の田子山富士塚がある。 柏町 寶幢寺 - 河童の伝承が残る寺院。江戸幕府第三代将軍徳川家光が鷹狩りの際休息した。 神明 神社 舘氷川 神社 長勝院跡 - 現在は御堂が取り壊され、敷地内に長勝院旗桜のみ残されている。 幸町 愛宕 神社 大六天社 上宗岡
- 敷島町
- 敷島 町(しきしままち)は、かつて山梨県中巨摩郡にあった町である。町名は合併時の公募による。 県中央北部、郡北東部に位置する。東西4キロメートル、南北15キロメートルの南北に長い帯状の町域で、中央部を亀沢川が南流し、中部の亀沢地区で東側を流れる荒川と合流する。北部は山岳地帯で茅ヶ岳や金ガ岳のほか、曲岳
- 甲斐市
- 1921年(大正10年) - 山縣 神社 がたつ。 1927年(昭和02年)4月1日 - 松島村と福岡村が合併して 敷島 村が発足。 1932年(昭和07年)信玄橋が作られる。 1946年(昭和21年) 10月17日 - 敷島 村が町制施行して 敷島 町となる。 山梨県立農林高校が玉幡飛行場跡であった現在地に移転した。
- 川原町 (前橋市)
- および南橘村大字上小出の一部、南橘村大字川原の一部に第二公園( 敷島 公園)が整備され開園。 1954年(昭和29年)- 6月に 敷島 公園敷地部分のみが前橋市に編入され、同市 敷島 町となる。この際、南橘村大字川原の小字は 敷島 町に引き継がれた( 敷島 町大泥)。 1954年(昭和29年)- 9月に勢多郡南橘村が前橋市に編入され、同市川原町となる。
- 和歌
- ほかには勅命によらずに編纂された私撰集がある。 和歌は「 敷島 (しきしま)」とも、また「 敷島 の道」とも呼ばれた。 敷島 とは大和国や日本のことを意味し、また枕詞のひとつでもあり「やまと」という言葉にあわせて使われている。即ち「 敷島 のやまとうた」「 敷島 のやまとうたの道」というつもりで用いられた言葉である。 上代歌謡
- 敷島神社 (吉野川市)
- 敷島神社 (しきじまじんじゃ)は、徳島県吉野川市鴨島町敷地に鎮座する 神社 である。 創立年は不詳。古くは西宮八幡宮と称していた。1909年(明治42年)に河辺八幡 神社 ほか五社を西宮 神社 に合祀。社殿を新築し新たに 敷島神社 と改称。 合祀された河辺(神戸)八幡 神社 には、式内社である天水沼間比古、天水塞比賣神
- 兵庫県指定文化財一覧
- 射楯兵主 神社 石造鳥居 〔姫路市〕 岩上 神社 本殿 〔淡路市〕 魚吹八幡 神社 楼門・摂社 敷島神社 本殿 〔姫路市〕 柏原八幡 神社 三重塔 〔丹波市〕 鴻池 神社 本殿 〔伊丹市〕 素盞嗚 神社 本殿・相殿2棟 〔宝塚市高司〕 素盞嗚 神社 本殿 〔宝塚市長谷〕 住吉 神社 石造燈籠 〔明石市〕 多田 神社
- 山梨県道25号甲斐中央線
- 国道52号交点甲斐市名取)供用開始。 2023年(令和5年)12月22日 - 田富町 敷島 線富竹Ⅰ期工区(国道52号交点真福寺入口交差点 - 国道20号交点山県 神社 北交差点間)供用開始。 国道20号(甲斐市富竹新田・山県 神社 北交差点 - 甲斐市竜王・竜王駅入口交差点) 山梨県道3号甲府市川三郷線(中巨摩郡昭和町上河東・常永小学校南交差点
- 鴨島町敷地
- 2004年(平成16年)10月1日 - 麻植郡鴨島町が川島町・山川町・美郷村と合併して吉野川市となり、現在の町名となる。 国立病院機構徳島病院 徳島県立鴨島支援学校 敷島神社 龍寿 神社 金刀比羅 神社 長戸庵 国道 国道192号 都道府県道 徳島県道238号川島西麻植停車場線 徳島県道240号西麻植下浦線 近藤廉平 - 実業家 [脚注の使い方]
企業データ
性蓮寺 1.13km
株式会社砂川工務店 0.95km
川口信用金庫/みずほ台支店 1.19km
株式会社プラスワン 1.11km
入間東部地区消防組合/消防署 1.09km
埼玉県警察署 0.75km
株式会社鈴木工務店 0.84km
富士見市役所/水谷出張所 0.73km
富士見市役所/水谷出張所 0.73km
株式会社フジミ建総 1.19km
JAいるま野/水谷支店 0.60km
富士見市立水谷放課後児童クラブ 0.60km
さくら記念病院 0.83km
株式会社三津穂 0.86km
株式会社東建社 0.79km
渡辺土建株式会社 0.75km
株式会社キョウユウ 0.83km
デイサービスセンターみずほ台 1.13km
富士見市立みずほ台第2放課後児童クラブ 1.13km
富士見市立みずほ台第1放課後児童クラブ 1.13km
株式会社ワイテック 0.37km
株式会社ベストライン 0.54km
水宮神社 0.00km
氷川神社 0.00km
宗教法人大應寺 0.06km
株式会社日翔 0.62km
天理教/富士前分教会 0.78km
大安建設株式会社 0.45km
富士見市役所/健康増進センター 0.90km
三浦病院 0.55km
地域包括支援センターふじみ苑 0.93km
特別養護老人ホームふじみ苑 0.93km
株式会社マルエフ 1.11km
創価学会富士見文化会館 1.06km