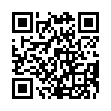Vinca Beta
道場寺
基本情報
- 所在地
- 〒177-0045
東京都練馬区石神井台1丁目16-7 - TEL / FAX
- 03-3996-0015
- URL
- 業種
- 寺院
- コメント
- 最寄り駅
- 西武池袋線 石神井公園 1080m
- 西武新宿線 上石神井 1270m
- 西武新宿線 上井草 1300m
- 周辺情報
- 練馬区立石神井図書館 公共図書館
- 練馬区立石神井小学校 小学
- 池淵史跡公園 観光公園
- 練馬区郷土資料室 各種資料館
- 石神井公園 観光公園
- 三宝寺 全国巡礼名所(武蔵野三十三観音)
- 石神井公園軟式野球場 野球場(スタンド完備無)
- 東京都立石神井公園 公園、緑地
- 練馬区立石神井公園ふるさと文化館 その他文化施設
- JA東京あおば石神井支店 銀行その他
- 石神井城 城跡
- 都立石神井公園 花の名所
- 三宝寺池 湖、沼、池、貯水池、潟、人工湖、浦(水部)
- ミニストップ石神井町5丁目店 ミニストップ
ウィキペディア検索
- 道場寺 (練馬区)
- 道場寺 (どうじょうじ)は、東京都練馬区石神井台にある曹洞宗の寺院。 1372年(応安5年)、豊島輝時の開基である。豊島氏の菩提寺として創建されたという。当初は臨済宗の寺院であったが、1601年(慶長6年)に曹洞宗に転宗した。 当寺には「北条氏康印判状」を所蔵している。内容は当寺に対して租税等を課さないと確約した保証書である。
- 郷照寺
- 本尊真言:おん あみりた ていぜい からうん ご詠歌:踊りはね念仏申す 道場寺 (どうじょうじ) 拍子(ひょうし)をそろえ鉦(かね)を打つなり 寺伝によれば、行基が神亀2年(725年)に一尺八寸(55 cmという説も)の阿弥陀如来を本尊として 道場寺 の名で開基した。大同2年(807年)に空海(弘法大師)が伽藍を
- 石神井台
- 域内に鉄道駅はない。 富士街道 新青梅街道 井草通り 上石神井通り 学芸大通り 旧早稲田通り - 三宝寺、 道場寺 などが沿道に立地する。 石神井川 都立「石神井公園」 三宝寺池 - 三宝寺池沼沢植物群落が天然記念物に指定されている。 石神井城址 けやき憩いの森
- 千葉県道298号絹郡線
- 富津市 - 君津市 千葉県道159号君津大貫線(信号交差点(絹)) 郡川 国道127号(郡交差点) 岩瀬川 宝幢寺 富津市立吉野小学校 金剛寺 道場寺 郡ダム 正福寺 ^ a b 君津土木事務所『道路現状一覧(令和2年4月1日現在)』(レポート)千葉県。https://www.pref.chiba
- 新田原駅
- 新田原駅(しんでんばるえき)は、福岡県行橋市大字 道場寺 にある、九州旅客鉄道(JR九州)日豊本線の駅である。 行橋市南部の住宅地域に存在し、北九州の通勤通学圏内にあり、ラッシュ時を中心に小倉方面への利用客が多い。当駅発着の列車もある。また、隣接するみやこ町豊津地区の最寄駅でもあるため、この地域の住民も利用する。
- 石神井公園
- 。池の名称の由来となり、太田道灌が当地へ移した真言宗寺院の三宝寺(江戸期まで末寺を擁していた本寺格)、豊島(輝時)氏が建てた曹洞宗寺院の 道場寺 (ねりまの名木、 道場寺 のクロマツあり)などもある。三宝寺の山門は三代将軍徳川家光が鷹狩の際に休憩に立ち寄った記録が残ることから「御成門(おなりもん)」と呼ばれ
- 三宝寺 (練馬区)
- 同公園にある三宝寺池は三宝寺に由来。 道場寺 (隣接) 石神井氷川神社 - かつては当寺が別当寺であった。 西武池袋線・石神井公園駅より徒歩約20分。 西武バス 石22・荻14・荻15系統、みどりバス(関町ルート) JA東京あおば下車 徒歩4分 拝観は日中の時間帯のみ無料。 [脚注の使い方] ^ 豊島氏の菩提寺は現在隣にある 道場寺 である。
- 福岡県道243号節丸新田原停車場線
- 終点:福岡県行橋市大字 道場寺 (日豊本線 新田原駅前、福岡県道244号稲童新田原停車場線終点) 国道10号(行橋市大字高瀬・高瀬交差点 - 行橋市大字 道場寺 ・新田原駅前交差点) 福岡県道244号稲童新田原停車場線(行橋市大字 道場寺 地内) 京都郡みやこ町 行橋市 日豊本線 みやこ町立節丸小学校
- 武蔵野三十三観音霊場
- 1993年(平成5年)4月2日に武蔵野三十三観音霊場会が再結成され、公式サイトも開設されている。また、ガイドブックが刊行されている。 第一番 長命寺 山門 第二番 道場寺 第三番 三寳寺 観音堂 第四番 如意輪寺 観音堂 第五番 多聞寺 本堂 第六番 全龍寺 第九番 實蔵院 第十二番 全徳寺 第十三番 金乗院 第十四番
- 慧観
- と共に荊州に往いた。司馬休之は高悝寺を建て慧観を請じて主となった。 鳩摩羅什の寂滅後、再び江南へ移り、荊州を経て都の建康に入った。 道場寺 に住したために、一般には、 道場寺 の慧観と称される。十誦律に通じた。 同じく南渡して建康の青園寺に住していた竺道生が、「悉有仏性説」に基づいた「頓悟成仏義」を主張し
企業データ
西脇医院 1.07km
石神井福音教会 0.99km
大角医院 1.14km
株式会社東京都民銀行/上石神井支店 1.12km
天理教東照分教会 1.19km
法音寺東京支院 0.95km
消防署/石神井消防署 0.76km
智福寺 1.08km
株式会社一本堂/下石神井店 0.71km
青嶋医院 0.76km
ゴールド交通株式会社/本社/営業所 0.91km
練馬区役所/石神井清掃事務所 0.96km
菅広医院 0.90km
下石神井三郵便局 0.82km
株式会社トイダ 1.13km
フローラ石神井公園 0.83km
株式会社朝日新聞社朝日新聞サービスアンカー練馬区ASA下石神井 0.97km
優っくりグループホーム石神井台沼辺 0.68km
西京信用金庫/石神井台支店 0.85km
釈迦本寺 0.42km
石神井バプテスト教会 0.63km
練馬区立石神井小第二学童クラブ 0.15km
練馬区立石神井小学童クラブ 0.15km
練馬区/石神井台児童館 0.80km
練馬区敬老館/石神井台 0.80km
東京あおば農業協同組合/セレモニーセンター 0.13km
野地医院 0.64km
東京あおば農業協同組合/とれたて村石神井 0.19km
東京あおば農業協同組合/石神井支店 0.19km
東京あおば農業協同組合/本店/共済部 0.19km
東京あおば農業協同組合/地域振興部 0.19km
三宝寺 0.09km
日本スポーツ芸術協会 0.71km
道場寺 0.00km
練馬区立石神井図書館 0.07km
氷川神社 0.27km
西大泉諏訪神社連絡所 0.27km
十善戒寺 0.96km
東京土建一般労働組合/練馬支部/南田中分会 0.57km
小林医院 0.74km
練馬区役所/石神井公園ふるさと文化館 0.15km
禅定院 0.57km
練馬区立南田中図書館 1.14km
練馬区/南田中児童館 1.18km
くまさん児童デイサービス 1.05km
株式会社メディカルアート 0.80km
山本皮膚科 0.94km
練馬区立石神井台けやき学童クラブ 1.20km
バンズ株式会社 0.75km
石神井郵便局/貯金・保険 0.69km
石神井郵便局/郵便 0.69km
菅原医院 0.86km
株式会社ガラテイア 0.62km
ワークショップ石神井 0.64km
土屋医院 0.97km
セントケア東京株式会社/セントケア練馬 0.82km
東京/石神井警察署 0.66km
豊島医院 1.05km
田村外科クリニツク 0.81km
株式会社けんしんケアサービス 0.96km
練馬区役所/区民事務所/石神井 0.84km
練馬区役所/石神井総合福祉事務所 0.84km
練馬区/在宅介護支援センター/石神井 0.84km
練馬区/石神井休日急患診療所 0.84km
練馬区役所/西部土木出張所 0.84km
練馬区/石神井歯科休日急患診療所 0.84km
ニチイのほほえみ石神井公園 0.80km
株式会社建設機械新聞社 0.95km
東京あおば農業協同組合/石神井公園支店 0.91km
宗教法人幸福の科学練馬西支部 0.91km
石神井公園駅前郵便局 0.97km
練馬区/デイサービスセンター/東大泉 1.16km
朝日生命保険相互会社/石神井営業所 0.90km
株式会社りそな銀行/石神井支店 0.97km
第一生命保険株式会社/池袋総合支社/石神井中央営業オフィス 0.97km
グループホームゆりの花 1.20km
三井住友信託銀行株式会社/石神井支店 1.20km
東京シティ信用金庫/石神井支店 1.20km
三洋測地株式会社 0.97km
株式会社三菱東京UFJ銀行/石神井公園支店 1.14km
練馬区/石神井児童館 0.94km
練馬区敬老館/石神井 0.94km
練馬区役所/男女共同参画センター 1.04km
練馬区立石神井町学童クラブ 1.04km
株式会社たまみずき 1.04km